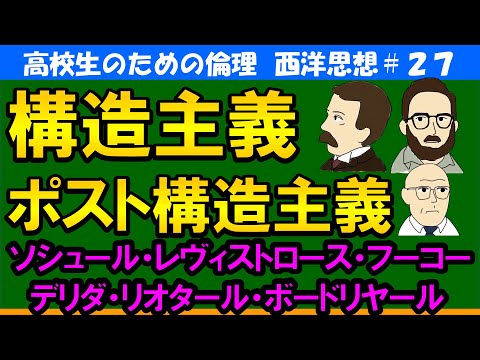導入
代数トポロジーにおけるフレヴィッチの定理は、 Xの基本群を使用した位相空間Xの最初の特異ホモロジー群の記述です。それは数学者フレヴィッツによるものと考えられています。
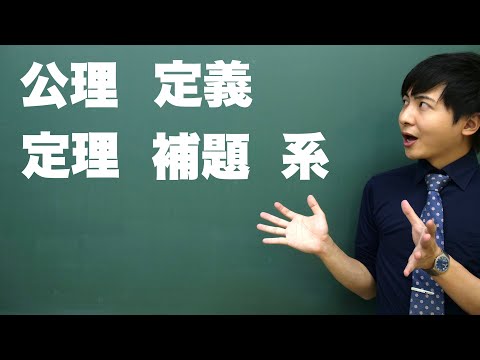
声明
弧で結ばれた位相空間の基本群これはπ 1 ( X , x )で表されます。 yが次の点の場合ただし、そのような同型写像は共役までしか定義されていません。
Gが群の場合、 [ G , G ]は、導出群と呼ばれる、 Gの交換子によって生成されるGの正規部分群を表します。群G a b := G / [ G , G ]はGのアーベル化と呼ばれます。 Gの最大のアーベル商であり、次の普遍的な性質によって特徴付けられます。
- Gからアーベル群への群射はG abを介して因数分解されます。
Gの内部自己同型は交換子を保存し、アーベル化されたG ab上の恒等性を商に渡すことによって誘導します。特に、(X,x) の基本群は基点xに依存しますが、そのアーベル化されたものはXの代数的不変量です。
特異相同性の構築は読者には既知であると想定されます。注意します
定理:
- X を円弧で接続された位相空間とする。靴紐$$ {f:[0,1]\rightarrow X} $$1 文字列としてのサイクルです。グループアプリは$$ {\Phi_X:\pi_1(X,x)\rightarrow H_1(X,\mathbf{Z})} $$Hurewicz 同型性と呼ばれる同型性を引き起こします。
- さらに、 Yも円弧で接続されていれば、任意のアプリケーションが続行されます。 $$ {g:X\rightarrow Y} $$群射を誘起する$$ {g_*:\pi_1(X,x)\rightarrow \pi_1(Y,g(x))} $$そして$$ {g_*:H_1(X,\mathbf{Z})\rightarrow H_1(Y,\mathbf{Z})} $$。これらの射は次のことを検証します。
言い換えると、
- 「オブジェクト」を関連付けるファンクターH 1 $$ {H_1(X,\mathbf{Z})} $$;
- 関手$$ {\pi_1^{ab}} $$X は「オブジェクト」にπ 1 ( X , x ) a b を関連付けます。ここで、基点xは任意に選択されます。
Hurewicz の定理は、関数Φの同型写像の存在を示します。
証拠
Hurewicz の定理は、群射の存在とその全単射性を述べています。 Hurewicz 射の単射性は、その全射性よりも多くの作業を必要とします。全単射性は、逆関数の明示的な構築を与えることによってここで確立されます。 Δ 0 は点、 Δ 1 = [0,1]は標準 1 シンプレックス、 Δ 2 は標準 2 シンプレックスであり、点は重心座標で (s,t,u) (s+t+u) によって識別されます。 =1。
Hurewicz射の存在
点xにおけるXのループfは連続写像です
このアプリケーションは群の射です。 Xからxまでの 2 つのループfとgの場合、
として

逆の構築
X は円弧で接続されているため、 Xの点yに対して、始点xと終点yを持つパスλ y を導入しましょう (ここでは選択公理が使用されます)。 Xのすべての 1-simplex fに対して、次を定義します。
残念なことに、ヨーψ λ ( f ) は経路λ yの選択に依存します。アーベル化された基本群のクラスについても同じことが当てはまります。マップψ λ はZ線形マップを誘導します。
技術的な議論 (詳細は後述) は、次の注目すべき結果を示しています。
- Ψ λのカーネルには 1 エッジ (2 シンプレックスのエッジ) が含まれています。
- 使用されるパスの選択における依存関係がすでに強調されているにもかかわらず、1 サイクルに制限されたアプリケーションΨ Λ は依存関係から独立しています。
実際、 Ψ λ は、制限と商への通過により、 λとは独立した射Ψ を誘導します。
この射Ψ は、Hurewicz 射の逆射Φ = Φ Xとなるように構築されました。
- Xからxへのヨーfで表されるπ 1 ( X , x ) a bの要素αの場合、イメージΦ X ( f )はfで表され、1 サイクルとして見られます。定義により、 ΨΦ(α) は次のクラスです。 $$ {\lambda_x*f*\lambda_x^{-1}} $$、 fの共役。したがって、アーベル化では、それらのクラスは等しくなります: ΨΦ(α) = α 。
- 任意の 1 単体fに対して、 $$ {\lambda_{f(0)}*f*\lambda_{f(1)}^{-1}} $$は 1 エッジを法とするfに等しい (以下の引数を参照)。すぐに、 σ を1 サイクルとすると、$$ {\Phi\circ\Psi_{\lambda}(\sigma)} $$は 1 エッジの和を法とするσに等しい。言い換えると、$$ {\Phi\circ\Psi} $$アイデンティティに値する$$ {H_1(X,\mathbf{Z})} $$。
- どちらか$$ {h:\Delta_2\rightarrow X} $$2シンプレックス。次のように定義されるhの「辺」を導入しましょう。
- f 0 ( s ) = h (0, s ,1 − s ) ;
- f 1 ( s ) = h ( s ,0.1 − s ) ;
- f 2 ( s ) = h ( s ,1 − s ,0) 。
- hのエッジは正確にf 0 − f 1 + f 2です。ただし、計算すると次のようになります。
- $$ {\Psi_{\lambda}(\partial h)=\left[\lambda_{f_0(0)}*f_0*\lambda_{f_0(1)}^{-1}\right]-\left[\lambda_{f_1(0)}*f_1*\lambda_{f_1(1)}^{-1}\right] +\left[\lambda_{f_2(0)}*f_2*\lambda_{f_2(1)}^{-1}\right]} $$
- $$ {=\left[\lambda_{f_0(0)}*f_0*\lambda_{f_0(1)}^{-1}\right]+\left[\lambda_{f_2(0)}*f_2*\lambda_{f_2(1)}^{-1}\right] +\left[\lambda_{f_1(1)}*f_1^{-1}*\lambda_{f_1(0)}^{-1}\right]} $$
- $$ {=\left[\lambda_{f_0(0)}*f_0*f_2*f_1^{-1}*\lambda_{f_0(0)}^{-1}\right]} $$
- ここで、 f 0 (1) = f 2 (0) 、 f 2 (1) = f 1 (1) 、およびf 1 (0) = f 0 (1)を使用しました。として$$ {f_0*f_2*f_1^{-1}} $$hの境界線では、このレースは収縮可能であるため、 π( X , f 0 (0))の単位要素を表します。金、$$ {c\mapsto \lambda_{f_0(0)}*c*\lambda_{f_0(0)}^{-1}} $$群射を定義する$$ {\pi_1(X,f_0(y))\rightarrow \pi_1(X,x)} $$上記の計算は、次のクラスを送信することを示しています。$$ {f_0*f_2*f_1^{-1}} $$の上$$ {\Psi_{\lambda}(\partial h)} $$。すぐに:
- $$ {\Psi_{\lambda}(\partial h)=e\in \pi_1(X,x)} $$したがって、$$ {\Psi(\partial h)=0\in \pi_1(X,x)^{ab}} $$。
実際、 μ が元のパスxの別の選択である場合、および
- $$ {\Psi_{\mu}\left[\sum_{i=1}^kn_i.f_i\right]=\sum_{i=1}^kn_i.\left[\mu_{f_i(0)}*f_i*\mu_{f_i(1)}^{-1}\right]} $$
- $$ {=\sum_{i=1}^kn_i.\left(\left[\mu_{f_i(0)}*\lambda_{f_i(0)}^{-1}\right] + \left[\lambda_{f_i(0)}f_i*\lambda_{f_i(1)}^{-1}\right]+\left[\lambda_{f_i(1)}^{-1}\mu_{f_i(1)}^{-1}\right]\right) } $$
- $$ {=\sum_{i=1}^kn_i.\left[\mu_{f_i(0)}*\lambda_{f_i(0)}^{-1}\right]-\sum_{i=1}^k \left[\mu_{f_i(1)}*\lambda_{f_i(1)}^{-1}\right]+\Psi_{\lambda}\left[\sum_{i=1}^kn_i.f\right]} $$
- $$ {=\Psi_{\lambda}\left[\sum_{i=1}^kn_i.f\right]} $$