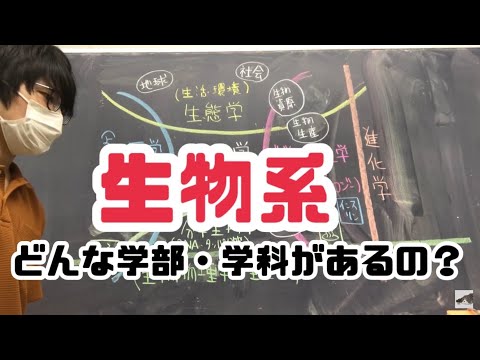導入
動物学(ギリシャ語のοον 、動物、動物、およびλόγος 、ロゴス、音声から) は、動物を研究する科学です。いくつかの分野を統合し、数多くの技術を使用することで、この科学は先史時代から何世紀にもわたってゆっくりと発展してきました。歴史的に、私たちに伝えられた動物学に関する最初の科学的考察はアリストテレスのものです。それ以来、動物種を分類する試みが数多く行われ、しばしば改訂されてきました。
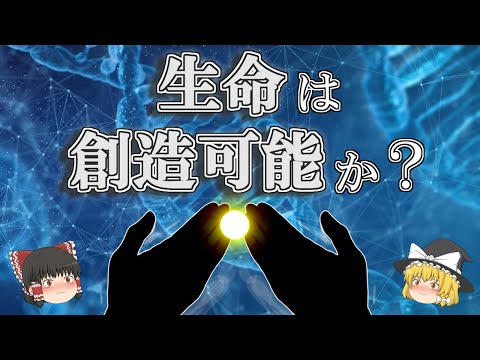
動物学と植物学の違い
動物を研究する動物学と植物を研究する植物学の境界は、今も昔も論争の的となっています。植物だと思われていた特定の生き物は、実は動物であることが判明しました。他の特定のケースについては、 21世紀の幕開けとなった現在でも依然として議論の対象となっています。これらの非典型的な生物は、技術的または科学的な進歩と発見 (特に顕微鏡法や DNA 分析) のおかげで、いずれかの科学に属することが変更されています。
ほとんどの後生動物が常に動物の中に分類されることに議論の余地はありませんでしたが、特定の後生動物は19世紀においても依然として「動物植物」(語源的には植物と動物)と呼ばれる特定のカテゴリーに分類されていました。このグループには伝統的に海綿動物、刺胞動物、有櫛動物、コケ植物が含まれていました。リンネはイカ、アメフラシ、ナマコなどの軟体動物、さらに棘皮動物(ウニやヒトデ)をこのカテゴリーに分類しました。ジャン=アンドレ・ペイゾネルがサンゴを動物として認識したのは 1744 年のことです。同様に、スポンジアリアは 1825 年まで動物として認識されませんでした。
原生動物の場合はさらに問題があります。ミドリムシや独立栄養食または従属栄養食を持つ特定のペリディヌス類など、それらの一部は長い間、この 2 つの分野の境界線上に置かれてきました。現代の分岐分類法により、緑色の系統(疑いの余地なく植物学と植物学に関係する)、オピストコン(動物学と菌類に関係する)、茶色の系統(生理学)、およびこの分野またはその分野のメンバーではないさまざまな系統を区別することが可能になりました。常に解決されます。
動物分類の進化
分類への最初の試み
レイは、行動基準や環境基準ではなく、解剖学的基準に基づいて動物を分類することを最初に提案しました。その分類、特に鳥類の分類は、リンネの研究までに最も進化しました。

動物の命名法
命名法は分類学と系統学に関連する学問であり、分類群と呼ばれる生きている(または生きていた)生物の学名の帰属と優先順位に関する規則を定義し、定めることを目的としています。今日でも使用されている二項命名法の基本規則を確立したのはリンネです。
古典派
分岐学は、1950 年代にドイツの昆虫学者 Willi Hennig によって開発された系統再構成の方法であり、文字または共形形態から派生した状態の共有に親族関係を基礎とします。
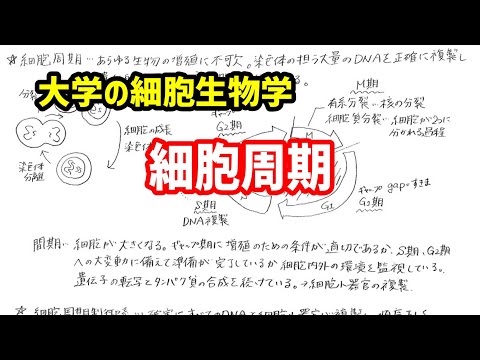
続く動物学の発見
多くの動物種は、現時点では研究されていないコレクションに保管されているか、まだ発見されていないため、現在動物学では知られていません。
これらの発見は、場合によっては重要になることがあります。たとえば、次のとおりです。
- 分類レベルでは、ポゴノフォアの全枝が認識され作成されたのは 1944 年で、このグループの最初の個体は1914 年に発見されました。
- 動物の大きさの観点から見ると、アフリカの哺乳類であるオカピは1900 年に発見され、1901 年に記載されました。体長4 メートルを超えるオオクチザメは1976 年に発見され、1983 年に記載されました。
- 種の進化に関する知識の観点から言えば、シーラカンスは 1938 年まで科学者に化石としてしか知られていませんでした。
- 文化レベルでは、クラーケン伝説の起源であるArchiteuthis属は、1857 年に Japetus Steenstrup ( Architeuthusという名前を付けた) によってのみ記載され、1860 年にJames Edmund Hartingによって確立されました。
シブリー・アールクイスト分類法は、「in vitro」DNA ハイブリダイゼーションに基づいています。これまでの鳥の分類を完全に覆すこの分類は、アメリカでは非常に急速に採用されましたが、ヨーロッパ、特にフランス語圏では非常に消極的で、かなりゆっくりと採用されました。