導入

乗算は、加算、減算、除算と並ぶ初等算術の 4 つの演算の 1 つです。
2 つの整数の乗算は、数回繰り返される加算とみなすことができます。たとえば、3 x 4 は 3 つの数値 4 の合計と見なすことができます。
- $$ {3 \times 4 = 4 + 4 + 4 = 12} $$
乗算は、長方形内に配置された要素を数えたり、長さと幅が既知の長方形の面積を計算したりするために使用できます。また、購入単価や購入数量が分かるので、購入価格を決定することも可能です。
乗算は、古典的な数値以外の集合 (整数、相対値、実数) に一般化されており、それらの間の複素数、関数、行列、さらにはベクトルを数値で乗算することができます。

一連の数値の乗算
整数での乗算
整数を別の整数で乗算することは、その整数をそれ自身に数回加算することを意味します。したがって、6 × 4 を掛けることは 6 + 6 + 6 + 6 を計算することになり、結果は4 × 6と呼ばれ、4 × 6 と書きます。6 × 4 の積をこの演算の結果と呼びます。この乗算では、6 は繰り返されるものであるため被乗数と呼ばれ、4 は 6 を何回繰り返す必要があるかを示すため乗数と呼ばれます。
ただし、4 × 6 は 6 × 4 にも等しいため、この区別はほとんど必要ありません。この 2 つの数値は、積の 2 つの項または因数と呼ばれます。
掛け算を足し算の繰り返しとみなすことは、長期的には効果的ではありません。したがって、1 から 9 までのすべての整数を乗算した結果を学習する必要があります。これが九九の目的です。
整数の乗算は次の特性を満たします。
- 最終結果 a ×b = b × a を変更せずに因子の順序を変更できます。乗算は可換であると言われます。
- 3 つの数値を掛け合わせる必要がある場合は、最初の 2 つを掛けてその結果に 3 番目の係数を掛けるか、最後の 2 つを掛け合わせてその結果に最初の数値を掛けます: (a ×b) × c = a × (b×c)。掛け算は結合的であると言われます。
- 和(または差)に数値を乗算する必要がある場合、最初に和を計算してその結果に数値を乗算するか、最初に和の各項にこの数値を乗算してから合計を実行するかを選択できます。 a + b) × c = (a × c) +(b × c)。 c を和の 2 つの項に分配したので、乗算は加算に対して分配的であると言います。
括弧は、操作を実行する順序を示します。実際には、括弧をドラッグしすぎないように、慣例により、乗算は常に加算の前に実行されるという優先順位ルールを使用します。したがって、4 + 5 × 2 を書くときは、4 + (5 × 2)、つまり 18 に相当する (4 + 5) × 2 ではなく、4+10 = 14 と読み取る必要があります。
- $$ {4 + 5 \times 2 = 4 + (5 \times 2) = 4 + 10 = 14} $$
- $$ { (4 + 5) \times 2 = 9 \times 2 = 18 \ne 4 + 5 \times 2} $$
このルールを運用優先度といいます。
最後の特性は比較に関するものです。 2 つの数値を特定の順序で配置し、それらに同じ厳密に正の数値を乗算すると、結果は同じ順序で配置されます。 a < b の場合、ac < b × c になります。正の整数による乗算は順序と互換性があると言われます。
かけ算に使われる記号は十字×(a×b)ですが、文字を使った計算では点も求められます。
やや特殊な操作が 2 つあります。
- 1 を掛けると項は変わりません: 1 × a = a × 1 = a。 1 は乗算にとって中立的な要素であると言われます。
- 0 と 0 の掛け算は常に 0 になります: 0 × a = a × 0 = 0。0 は掛け算を吸収する要素であると言います。
小数での乗算
小数の乗算には、積を任意の順序で乗算できるという事実を利用します。たとえば、43.12 に 1.215 を掛けようとすると、次のようになります。
- $$ { 43,1 \times 1,215 = \left(431\times \frac 1{10}\right) \times \left(1215\times \frac 1{1000}\right)} $$
- $$ { 43,1 \times 1,215 = (431 \times 1215) \times \left(\frac1{10}\times \frac1{1000}\right)} $$
- $$ { 43,1 \times 1,215 = (431 \times 1215) \times \frac1{10000}} $$
ここからルールが生まれます。2 つの小数を掛け合わせるには、2 つの数値の小数点以下の桁数を数え、それらを合計します。次に、カンマを考慮せずに積を実行します。最後に、最終結果に小数点を配置し、以前に取得した合計と同じ数の桁を右側に残します。
- 3.15 × 1.2= ? (小数点以下は 3 桁で、最初の数字が 2、2 番目の数字が 1 です)
- 315 × 12 = 630 × 6 = 3780
- 3.15 × 1.2 = 3.780 = 3.78
負の数との乗算
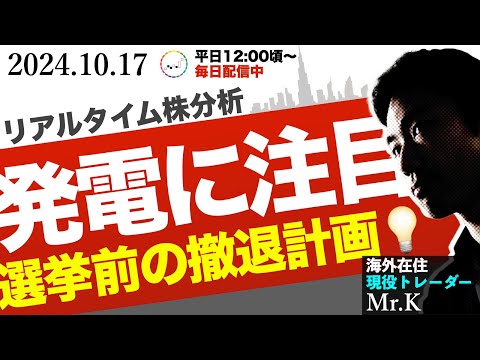
4 回の積 (-6) は、(-6) を 4 回繰り返した合計であることがわかります。つまり、(-6) + (-6) + (-6) + (-6) = -24
また、積 (-4) と (6) を 4 回引いた数字の 6 として見ることもできます。したがって、(-4) × 6 の積を実行すると 24 が削除され、(-4) × 6 = -24 と書きます。
最後に、(-4) と (-6) の積は、4 回引いた数 (-6) として表示されるので、-24 を取り除くことになります。 – 24 を引くと 24 を足すことになるので、(-4) × (-6)= 24
これらの例は、符号付きの数値に関する規則を説明します。 2 つの符号付き数値の積を計算するには、絶対値の積を実行し、2 つの項の符号が異なる場合はその結果に符号 – を割り当て、2 つの項の符号が同じ場合は符号 + を割り当てます。
これらのルールは次のように要約されます。
- より少ないほどより多くに等しい
- マイナス×プラスはマイナスに等しい
- プラスとマイナスはマイナスに等しい
- プラスバイプラスはプラスに等しい
相対整数での乗算は、自然整数での乗算と同じ性質を持ちます (可換、結合、加算の分配的です) が、1 つの例外があります: 順序が常に保持されるわけではありません: 2 つの数値が特定の順序で配置され、それらを乗算した場合厳密に正の整数を指定すると、順序は維持されます
- -2 < 3 および (-2) × 4 < 3 × 4
しかし、負の数を掛けると、順序が逆になります。
- (-2) < 3 および (-2) × (-4) > 3 × (-4)
分数での掛け算
2 つの分数を掛けることは、分子と分母を掛けることを意味します。
- $$ {\frac ab \times \frac cd = \frac{a \times c}{b \times d}} $$
実数での乗算
これは、前の乗算を一般化したものです。同じ特性を保持します。
逆行する
乗算の数値の逆数は、1 を得るために乗算する必要がある数値です。
例えば、
- 10 × 0.1 = 1 なので、10 の逆数は 0.1 です。
- 2 × 0.5 = 1 なので、2 の逆数は 0.5 です。
- の反対$$ {\scriptstyle \frac 34} $$東$$ {\scriptstyle \frac 43} $$なぜなら$$ {\scriptstyle \frac 34 \times \frac 43 = \frac {12}{12} = 1} $$
数 a の逆数が注目されます
それで
- πの逆数が注目される$$ {\scriptstyle \frac 1{\pi}} $$
- 2の逆数が注目される$$ {\scriptstyle \frac 12 = 0,5} $$
数値のセットによっては、そのセット内で常に逆数が見つかるとは限りません。
- すべての整数の中で、1 と -1 だけが逆数を持ちます
- 数値の集合が何であれ、0 に a を掛けると常に 0 が得られ、1 になることはないため、0 には逆数がありません。
- 有理数の集合と実数の集合では、0 を除くすべての数値は逆数を持ちます。
初等数学の 4 番目の演算である除算は、逆数による乗算とみなすことができます。
複数
数値 a が数値 b の倍数であると言うのは、それが b と整数 (自然または相対) を乗算した結果である場合です。
- a = k ×b となるような相対整数k が存在する場合に限り、a は b の倍数になります。
a と b が整数の場合、a は b で割り切れるとも言います。
身体の概念
有理数のセットと実数のセットでは、乗算に関する次のプロパティが見つかります。
| 結合性 | すべての a、b、c について、a ×(b × c) = (a × b) ×c |
|---|---|
| 可換性 | すべての a と b について、a × b = b × a |
| 中立的な要素 | すべてのa について、a × 1 = 1 × a = a |
| 逆行する | ゼロ以外のすべての a に対して、a × a -1 =1 となる-1 が存在します。 |
| 分配性 | すべての a、b、c について、(a + b) × c = (a × c) + (b × c) |
| 吸収要素 | すべての a について、a × 0 = 0 × a = 0 |
| 注文 | すべての a > 0、すべての b と c について、b < c の場合、ab < ac |
これらのプロパティは、これらのセットの加算によって所有されるプロパティに関連付けられており、
