導入
波力学における分散とは、分散媒体中の波に影響を与える現象、つまり、波を構成する異なる周波数が同じ速度で伝播しない現象です。私たちは、光、音、波など、あらゆる種類の波でこの現象に遭遇します。虹は大気による分散の現れです。
真空は光波を分散させません。光の速度はその周波数に依存しません。
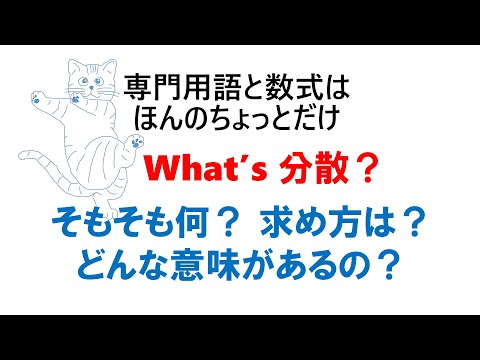
分散媒質中の波
正弦波は、周波数νまたは脈動ω = 2πν (単位 rad/s)、およびノルムk = 2π / λ (単位 rad/m) の波数ベクトルによって特徴付けられます。ここで、 λ は波の長さです。
次に、2 つの異なる特性速度があることがわかります。
- 位相速度$$ {v_\phi=\frac{\omega}{k}} $$これは波面の動きに対応します。
- そしてグループスピード$$ {v_g=\frac{\partial \omega}{\partial k}} $$これは、波のエンベロープの変位、つまりエネルギーの変位に対応します。
これら 2 つの速度は、環境の種類に応じて異なる動作をします。
- 媒質が非分散性である場合、つまりv φ がkに依存しない場合、 ωは必然的にkに比例します。したがって、2 つの速度は等しく一定であることがわかります。
- 媒質が分散性の場合、これら 2 つの速度は等しくなくなり、 kに依存します。
これらの特性は、波束の伝播の研究において顕著です。波束は、定義上、異なる波長のいくつかの正弦波の重ね合わせです。その速度はグループ速度に対応していることがわかります。
v g = v φなどの非分散媒質では、波束の速度はそれを構成する正弦波と同じです。次のアニメーションはこの現象を示しています。
波束内のきついうねりは、変形することなく全体として動きます(波束の中心にある最も高いうねりは中心に残ります)。
次のアニメーションに示すように、分散媒体では、波束はそれを構成する波と同じ速度では進みません。
きつい凹凸はパッケージの形状よりもゆっくりと進むため、パッケージ内をスクロールします。
物理学の他の分野における分散
分散は物理学のあらゆる種類の波で発生します。例としては、海底が平らでない場合の波、プラズマ波、音、虹などが挙げられます。
光学分野
屈折率の変化
媒質はその屈折率n = c / vによって特徴付けられます。ここで、 c は真空中の光の速度、 v は考慮される媒質中の光の速度です。光線の経路上でこの屈折率が変化すると、光線の逸脱、つまりスネル・デカルトの法則に従って屈折が生じます。
したがって、伝播媒体が分散性の場合、伝播速度、したがって屈折率は周波数に依存します。光線の偏差は周波数、つまり色に依存します。これはガラスなどの材料で観察されます。青色の光線は赤色の光線よりも大きく偏り、したがって色が分離されます。この観察はプリズムの場合に知られています。
可視光における透明媒体の屈折率の変化は、いわゆるコーシーの法則に従います。
結果
光波は、波長の関数として放射される強度の分布であるスペクトルによって特徴付けられます。可視光の場合、波長は目で認識される色に関連付けられます。一般に、光波は多色性です。つまり、光波は複数の波長で構成されています。したがって、太陽光には目に見えるほとんどの色が含まれています。分散により、それらを分離することが可能になり、放射線を構成する色を視覚化することができ、特に分光分析を行うことが可能になります。
日常生活で目に見える例の 1 つは虹です。屋外で観察できる虹は、空気中の水滴による太陽光の分散の結果です。虹現象を計算すると、それを見るためには常に太陽に背を向けなければならないことがわかります。これは簡単に確認できることです。
しかし、分散は光学システムの性能を制限するという結果ももたらします。次のものが挙げられます。
- 光ファイバーの波長分散により、伝送の帯域幅が制限されます。分散媒質では、各波長が異なる速度で伝播するため、送信中にパルスが一時的に広がります。とりわけ、スペクトル幅が狭いレーザーダイオードを使用するのはこのためです。
- 光学システムでは、波長ごとの偏差の違いは色に応じて異なる経路を意味し、その結果色収差が発生します。それらは波長に応じて変化する収束点によって現れ、画像の誤ったカラー化を引き起こします。このテーマについては、たとえば「 天体望遠鏡 」と「 光学顕微鏡 」の記事を参照してください。
分散媒の特性評価
分散媒質内の屈折率を測定するには、可視スペクトルの中央に近いヘリウムの D線(真空中の波長 587.6 nm) などの基準単色放射が必要であり、これがよく使用されます。
放射線 D の場合、20°C における水の絶対屈折率n D は1.333 です。通常のガラスの値は 1.511 ~ 1.535 です。空気の屈折率は、通常の温度と圧力の条件下では 1.000 292 6 に等しくなりますが、真空中の波長にも依存します。このような小さな差( n − 1)は、2 つの光線間の干渉によってこの精度で測定されます。一方の光線は空気を通過し、もう一方の光線は空気の入っていない管を通過します。緑と赤の屈折率のわずかな違いにより、海に沈む夕日(雲のない非常に良い天気の場合)に「緑の光」が生成されます。緑の光は、非常に斜めに交差するため、赤の光よりも少しずれています。空気層。その結果、最後の緑の光線は最後の赤の光線の 1 ~ 2 秒後に消えます。
可視範囲(真空中の波長 380 nm ~ 780 nm)では、分散は収斂性によって特徴付けられます。次に、収束性が 50 より小さいか大きいかに応じて、ガラスはクラウン タイプ (分散性が低い) またはフリント (分散性が高い) に分類されます。収斂性はアッベ数とも呼ばれ、次の式で定義されます。
- $$ {\nu = \frac{n_D – 1}{n_F – n_C}} $$、
F と C は 2 本の水素の線を示します (真空中の波長λ F = 486.1 nm およびλ C = 656.3 nm)
プリズムによる分散
ガラスなどの物質による散乱は、太陽光の分析に使用されてきました。ニュートンのプリズムを使った実験は有名です。実証実験では常にプリズムが使用され、光が 2 つのジオプターを通過するときに良好な色の分散を観察することができます。
実際には、分散を最適化しながら偏差を最小限に抑えるために選択された、実際には 3 つの隣接するプリズムで構成される光学システムである「直視プリズム」も使用します。
ネットワークによる分散
ネットワークとは透明な縞模様の板(平行縞数百本/mm)で、スリットに相当します。したがって、干渉を受ける可能性があります。
単純な放射の場合、縞の交互が得られます。白色光の場合、これらは中央の白いフリンジの周りで観察される色のグラデーションであり、これが対称軸を形成します。
